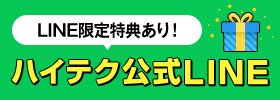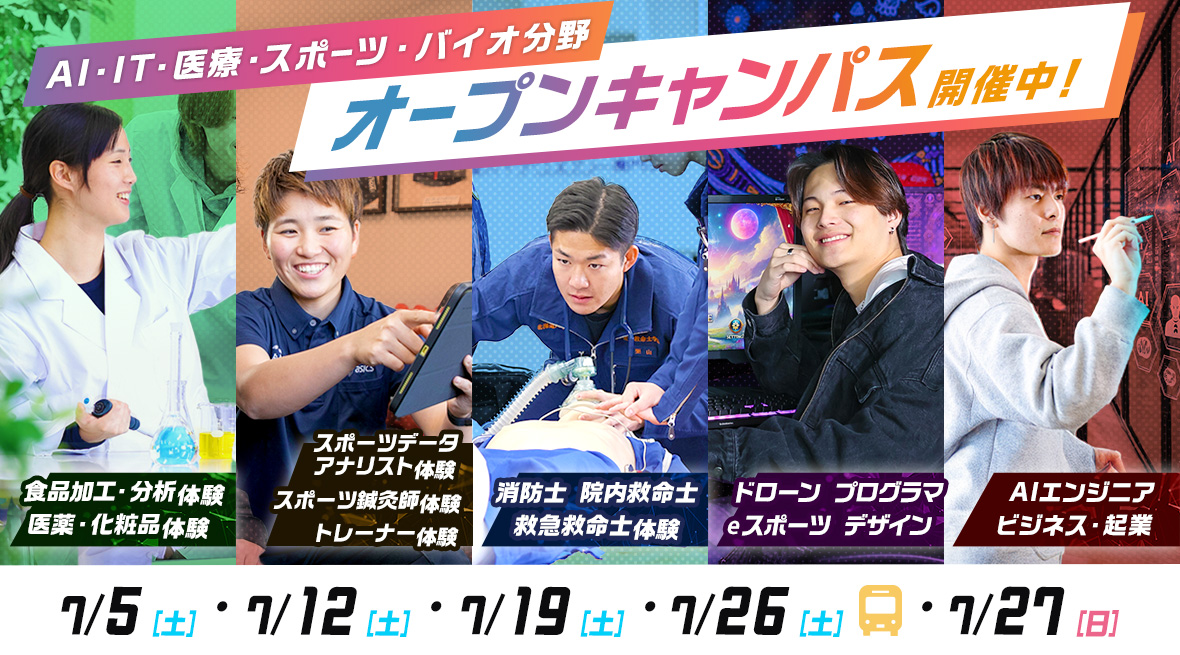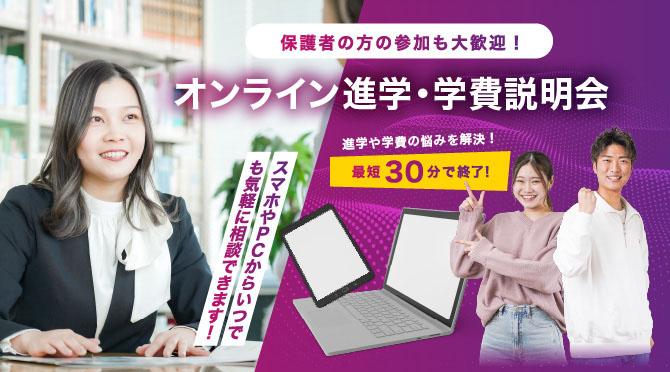救急救命士と看護師はどちらも医療現場で人の命を救う専門職ですが、両者の役割や資格、活躍の場には違いがあります。
医療現場のひっ迫や人材不足が懸念されている近年、救急救命士や看護師への需要はますます高まっています。
この記事では、救急救命士と看護師の仕事内容や試験内容、年収などを比較して解説します。それぞれの仕事の特徴や違いについてくわしく見ていきましょう。
【目次】
救急救命士とは?

医療系国家資格を持つ救急救命士は、傷病者を医療機関に搬送するまでの間に医師の指示のもと必要な処置を施す仕事を担います。
救急救命士が活動する場は消防機関をはじめ、自衛隊(陸・海・空)、海上保安庁、警察組織、医療機関、民間救急会社、警備会社など多岐にわたります。
救急救命士は、病院前救護(プレホスピタルケア)の質的向上に努めており、重篤な状態にある方や心肺停止の方を含む重症傷病者の救命率を高め、社会復帰につなげることを目指しています。また、近年では大幅な法改正により病院内でも活躍の場が拡がっており入院加療の手前までの処置等を担うことも可能となりました。
救急救命士になるには
救急救命士になるためには、厚生労働大臣および文部科学大臣が指定する大学・救急救命士養成校に入学し教育を受け、国家試験に合格する必要があります。
救急救命士養成所(専門学校)で所定の教育課程を修了
大学の救急救命学科(4年制)を卒業
大学および養成校では、基礎医学から実技まで幅広い知識を学び、卒業後に国家試験の受験資格を得られます。国家試験に合格後、正式に救急救命士として活躍できるようになります。
看護師とは?

看護師は、病気やけがの患者さん、また出産後の女性などに対して、専門的なケアと医療サポートを提供する医療専門職です。
その特徴は、単に症状を診るだけでなく、「人を看る」という独自の視点を持っていることです。そして、患者さんの身体的な状態はもちろん、心の健康状態や生活環境、文化的背景などを含めて理解し対応します。
看護師の活動範囲は、従来の病院や診療所勤務という枠を超えて大きく広がっています。在宅医療を支える訪問看護ステーションや、高齢者向けの介護施設、各種福祉施設など、人々の健康と暮らしを支える場所で、その専門性を活かした仕事を展開しています。
日本の高齢化が進展する中で、看護師の役割はますます重要とされているため、より多くの場面で看護師の専門的なスキルが必要とされ、その活躍の場はさらに拡大していくでしょう。
看護師になるには
看護師になるためには看護師国家試験への合格が必須です。まずは、厚生労働大臣または文部科学大臣指定の以下のいずれかの大学・短期大学・専門学校・高等学校看護科で教育を受けます。
看護専門学校(3年課程)
看護大学(4年制)
看護短期大学(3年制)
高等学校看護科(中学卒業後専攻科含め5年制一貫校)
各教育機関で必要な単位を修得後、看護師国家試験の受験資格が与えられます。
救急救命士と看護師の資格の違い
救急救命士と看護師の資格の違いを表にまとめました。
| 資格名 | 救急救命士 | 看護師 |
| 法律 | 救急救命士法 | 保健師助産師看護師法 |
| 資格取得までの年数 | 約3年 | 約3年 |
| 国家試験受験者数
(2024年) |
約3,000名 | 約63,000名 |
| 合格率 | 約95% | 約87% |
国家試験受験者数データ参考:
厚生労働省「第47回救急救命士国家試験の合格発表」
厚生労働省「第113回看護師国家試験の合格発表」
救急救命士・看護師はどちらも国家資格です。次にそれぞれの資格をくわしく解説します。
救急救命士の資格

救急救命士の資格取得について解説します。
受験資格
救急救命士の資格を取得する方法は主に2通りあります。
一つ目は救急救命士の養成課程がある大学、または専門学校で所定のカリキュラムを修了し国家試験を受けることです。
もう一つの方法は、消防職員として採用された後に国家試験を受ける方法です。ただし、消防職員から救急救命士を目指す場合は、消防職員としての5年または2,000時間以上の救急業務経験と、養成所で6か月以上の講習の受講が求められます。また、各自治体での予算状況や本部内選抜試験等を経て養成所へ受講派遣有無を決定するため希望した消防職員が救急救命士養成されるわけではありません。
試験内容
試験は筆記試験で、救急救命士として必要な知識と技能が評価されます。救急救命士の問題は必修問題・一般問題・状況(救急現場想定)設定問題があります。特に必修問題は80%以上の正答率かつその他の問題では60%以上の正答率を達成することで国家試験合格となります。試験科目には以下のようなものがあります。
医学概論
救急症候・病態生理学
疾病救急医学
外傷救急医学
処置各論
難易度
救急救命士は大学や専門学校のような養成所であれば座学や実技、学外実習等のカリキュラム(総時間数2500時間以上で指定単位数を取得)を全て満たし受験資格を得ることで国家試験を受験でき上記基準を超えると、資格取得が叶います。2024年の救急救命士国家試験の合格率は94%でした。
看護師の資格

次に看護師の資格取得について解説します。
受験資格
看護師になるには、看護学校等での専門的な学習と実習が求められます。看護専門学校や大学を卒業し、所定のカリキュラムを修了した後に、試験を受けることができます。
試験内容
看護師の試験は筆記試験で、医学や看護学の基礎的な知識が問われます。看護師国家試験の問題は必修問題・一般問題・状況設定問題の3種類です。出題される科目には以下のようなものが含まれます。
人体の構造と機能
疾病の成り立ちと回復の促進
健康支援と社会保険制度
看護学(基礎・成人・老年・小児・母性・精神)
在宅看護論
難易度
看護師の国家試験の合格率は、ここ10年は80〜90%であり、受験すれば高い合格率で資格取得が可能といえます。
ただし、受験資格を取得するまでには大学や専門学校などで専門の教育を数年かけて学ぶ必要があり、さまざまな知識を習得したうえで受験資格を得て国家試験に臨むことが大切です。
救急救命士と看護師の仕事内容の違い

それでは救急救命士と看護師の仕事内容の違いについて見ていきましょう。
救急救命士の仕事内容
救急救命士は、救急現場や救急車内で搬送する間もしくは医療機関に努める救急救命士は救急外来おいて医師の指示のもと特定行為と言われる点滴や薬剤投与、器具を用いた気道確保等の処置をしながら傷病者の症状悪化を防止し、命を守るための初期対応を実施します。
かつては救急隊員の医療行為は禁じられてきましたが、心肺停止となった人の救命率の低さや、社会復帰が叶わない人も多いことが背景となり、限られた処置しか許されない状況下で救急隊員からの苦しみの声が挙がったことなどから法律が施行されました。このことから一定の条件の下であれば救急救命士も医療行為が行えることとなりました。
医療技術の進歩や超高齢化社会など社会のニーズに応じ、救急救命士に認められる医療行為の範囲は徐々に拡大してきています。
気管挿管や薬剤投与などのより高度な救命処置も可能となり、プレホスピタルケア(病院前救護)の質の向上へとつながっています。
看護師の仕事内容
看護師は医師による診断と治療方針に基づきながら、専門的な医療ケアと生活支援を両立して提供する仕事です。
現代の医療は高度化・専門化が進む中、看護師は単なる医療処置の実施者としてだけではなく、患者さんと医療スタッフの架け橋としての役割も果たしています。
また、入院生活や治療過程におけるさまざまなシーンで、患者さんやご家族に対してアドバイスを行い、退院後の生活に向けた支援も行います。
このように、看護師には医療の専門家としての確かな知識や技術はもちろんのこと、患者さん一人ひとりの状況や気持ちを深く理解してその人らしい生活ができるように支える、豊かな人間性も求められています。
救急救命士と看護師の活躍の場の違い

次に、救急救命士と看護師の活躍の場の違いについて紹介します。
救急救命士の活躍の場
救急救命士は、従来の救急車内での救命活動を中心としながらも多岐に渡る場所で活動しています。救急救命士の活躍の場を見ていきましょう。
救急車での活動:現場から病院までの搬送中における特定行為を含む救急救命処置
災害医療:大規模災害が発生したときの救助活動や応急処置
イベント会場:大規模イベントでの緊急事態に備えて待機・救護の担当
企業内救命救護:工場や大規模施設での救護室勤務
自衛隊・海上保安庁:軍事や海上での救助活動や洋上救急任務(特定行為実施)
医療機関:救急外来での初期対応
教育機関:救急救命士養成課程教員
救急救命士の多くは基本的に消防職員として消防機関に所属し消火隊員・救助隊員・救急隊員・通信指令員等として活躍していますが、前述した法改正が行われたことで、病院内でも救急救命士の活躍の場は広がっています。
看護師の活躍の場
看護師は、医療と生活の両面からサポートを行う専門職として広い活動範囲を持っています。
医療機関では、病院内の各診療科での看護業務がメインです。また、クリニックでの外来や医師の処置の補助をしたり、健診センターでの保健指導を行ったりすることもあります。病院の手術室を専門に、医師の補助として処置を行う看護師もいます。
地域医療・福祉の場にも看護師の活躍場所があります。たとえば、訪問看護ステーションでの在宅ケアや介護施設での医療的ケア、デイサービスでの健康管理などです。
看護師の中には、保育園や学校での保健室に勤務する場合や、企業の健康管理室での産業看護師として働くこと、保健所での地域保健活動などで活動する人もいます。
そのほかにも、市区町村の保健センター、スポーツチームのメディカルスタッフ、製薬会社など看護師の活躍する場は広くあります。
救急救命士は傷病者に対し、主に緊急時の関わりであるのに対し、看護師は急性期から慢性期までの長期的な関わりを持ちます。また、活動の焦点も両者では異なり、救急救命士は生命の危機に対して即時的な対応を行い、看護師は治療と生活の質向上を含めた総合的なケアを行います。
業務の範囲も、救急救命士は救命措置を中心であるのに対し、看護師は基礎的な医療行為から生活支援まで幅広いケアを実施します。
このように、両職種とも医療の専門家でありながら、それぞれの特徴を活かした独自の役割を担っており、現代の医療体制において相互に補い合う重要な存在なのです。
救急救命士と看護師の年収の違い
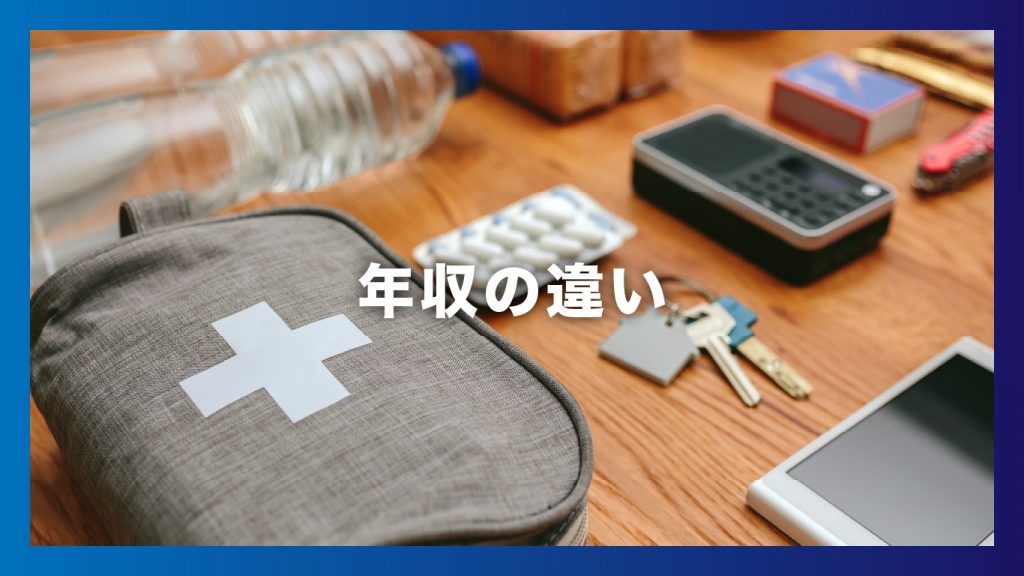
ここからは、救急救命士と看護師の年収の違いを見ていきましょう。
救急救命士の年収
救急救命士の多くは地方公務員として消防署に勤務しており、その給与は自治体によって異なります。2023年度の地方公務員給与実態調査結果の「職務区分別職員数及び平均基本給月額」によると、消防職員の平均基本給月額は約31万6,900円(給料のみ)です。また、平均年収は約635万円とされています。新卒の短大卒区分採用職員で基本給は18万円前後、大卒区分採用で19万円程度です。
給料以外には、扶養手当・地域手当が支給されます。また、年に1回の昇給、年に2回の賞与もあります。
病院内を活動拠点とする「院内救命士」という仕事もあり、この場合は民間の病院で働くことが可能です。その場合、年収アップにつながる可能性があります。
また、持っている資格に応じて手当が支給されるケースもありますが、各地方自治体によって規定があるため、資格手当が必ず含まれるとは限りません。
看護師の年収
次に、看護師の年収を見ていきましょう。
初任給については高卒で看護師養成学校の3年課程を卒業した新卒看護師の平均給与額は約20万4,000円。大卒の新卒看護師は約21万円です。
看護師は勤続年数を重ねるにつれて給与額もアップします。勤続10年の看護師の平均給与は約24万円とされています。
看護師の年収は以下の条件によって変わります。
年齢
勤続年数
病院(病床)の規模
役職
勤務形態(正社員・パート)
専門資格(専門看護師・准看護師)
これらのほかにも、夜勤や休日、時間外勤務に対して手当が加算されます。手当に関しても、勤務先によって金額は異なります。
近年の医療人材不足を背景に、救急救命士と看護師ともに待遇改善が話し合われる傾向にあり、今後の収入増加も期待できるでしょう。
救急救命士と看護師が行う医療行為の違い

救急救命士と看護師は共に医療従事者ですが、両者が行う医療行為には違いがあります。それぞれが行う医療行為について見ていきましょう。
救急救命士の場合
救急救命士には「特定行為」と呼ばれる医療行為があります。これは、医師からの具体的な指示を受け、決められた手順書(プロトコル)に基づいて医療行為(救急救命処置)を行うものです。
救急救命士は以下の5つの特定行為を行えます。
-
気管へチューブを挿入し気道を確保
-
心肺機能停止状態の傷病者への静脈路確保のための輸液
-
心臓機能停止状態の傷病者へのアドレナリン(薬剤)投与
-
低血糖による発作を起こした傷病者へのブドウ糖溶液投与
-
心肺機能停止前の重度傷病者への静脈路確保および輸液
これらのうち、4番目と5番目は2014年に国から実施許可が下りた医療行為です。
これら2つの行為ができるようになったことから、今まで医療機関に到着してから治療を開始ししていたことが搬送中に少しでも早く処置を開始できるようになり心肺停止に至る前に必要最低限度の処置をしながら医師へ引き継ぐことが可能になりました。
救急救命士が特定行為を行う場合、医療機関との連携が必須です。今後も救急救命士の処置範囲が拡大されることが予想され、また、救急救命処置の質向上のためにもメディカルコントロールを行う医療機関とのさらなる連携強化が求められています。
救急救命士には上記の特定行為のほかにも医師の包括的な指示により以下の処置が認められます。
小児科・産婦人科・精神科範囲の処置
心電図や血圧計、聴診器を使用すること
吸引器や喉頭鏡を使用した異物除去
酸素吸入器を使用する酸素投与
血糖測定
エピペンの使用
電気的除細動 など
看護師の場合
看護師ができる医療行為は「相対的医療行為」と呼ばれるものです。これは、医師および歯科医師の管理や指示があれば、実施が可能な医療行為のことです。
相対的医療行為には、注射・点滴・採血、そして導尿が含まれます。そして、看護師のなかでも医師の手順に従うことを前提に所定の研修を修了している場合、自身の判断での特定行為(治療の補助)が実施できるのは特定看護師といいます。
特定看護師が行う特定行為は38行為21区分あります。
呼吸器関連
循環器関連
心嚢ドレーン管理
胸腔ドレーン管理
腹腔ドレーン管理
ろう孔管理
中心静脈カテーテル管理
栄養に係るカテーテル管理
創傷管理
創部ドレーン管理関連
動脈血液ガス分析関連
透析管理関連
栄養および水分管理に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連
血糖コントロールに係る薬剤投与関連
術後 疼痛管理関連
循環動態に係る薬剤投与関連
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
皮膚損傷に係る薬剤投与関連
日本は超高齢化社会を迎えており、病床数のひっ迫や医師看護師不足などが懸念されています。その中で看護師の役割の拡大は重要です。
難易度の高い医師の診療の補助を、医師による手順もとに実施できる特定看護師は、医師の到着を待たずに病院内でも、訪問看護先でも行えるため、患者さんの病状悪化を防ぐことにつながります。
解説したように、救急救命士と看護師は異なる場面で、それぞれの専門性を活かした医療行為を行っています。救急救命士は緊急時の救命処置に特化し、看護師はより包括的な医療ケアを提供する役割を担っているのです。
まとめ
救急救命士と看護師は、人々の命と健康を守る医療専門職として、それぞれ異なる重要な役割を担っています。救急救命士は、救急現場から病院到着までの限られた時間内で、生命の危機に直面した傷病者へ救急救命処置を行います。一方、看護師は医療機関を中心に、患者の治療から回復まで、長期的な視点で総合的な医療ケアを提供します。
救急救命士は救命のための緊急処置に特化し、看護師は日常的な治療補助から療養上の世話まで幅広いケアが担当です。両職種とも、現代の医療体制において相互に補完し合う重要な存在です。
北海道ハイテクノロジー専門学校の救急救命士学科では、救命・消防の現場と学ぶ実践教育や最先端テクノロジーを活用した救急救命士の養成などを行い、命をつなぐ救急救命士の養成をしております。
学科情報はこちら
消防士・救急救命士を目指すならハイテクへ!
各種手厚いサポートや機材・実習の様子を見学にいらしてください!