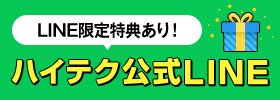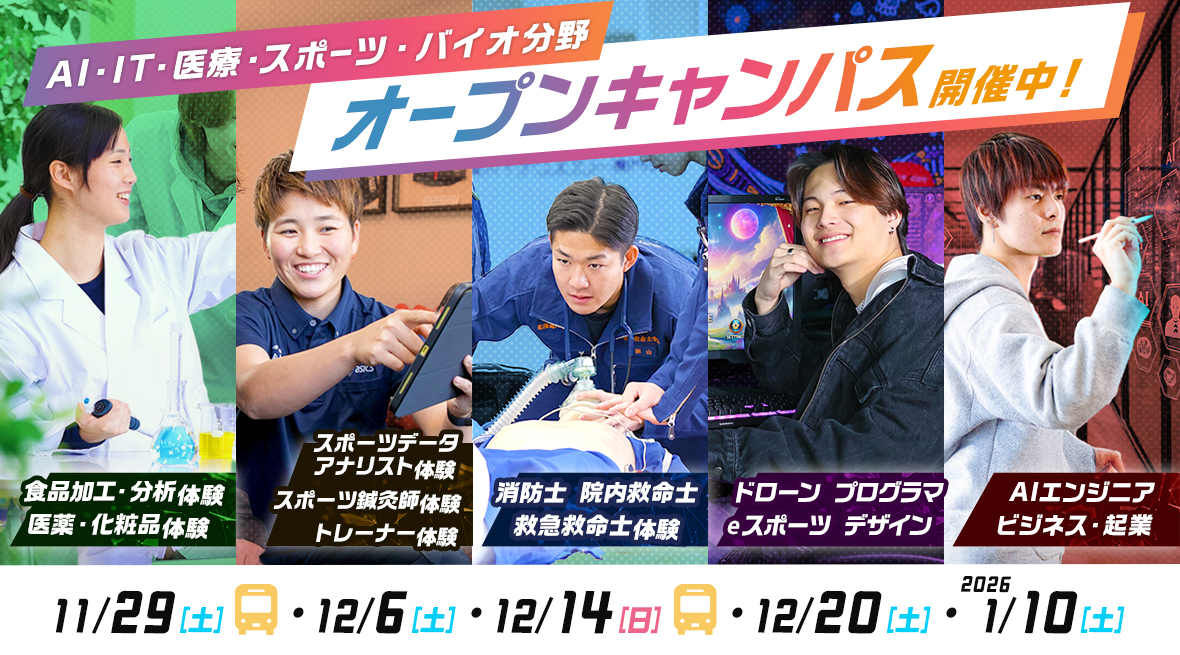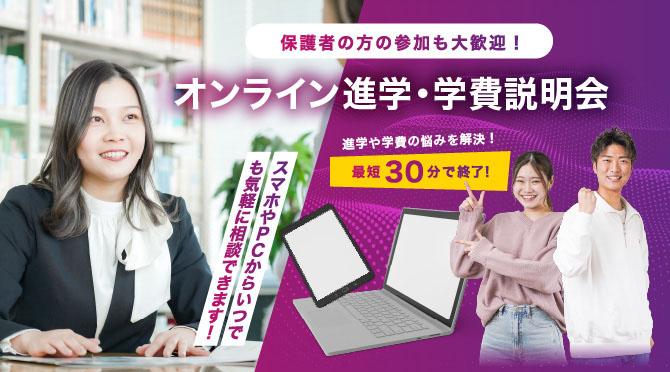消防士は地域住民の命や財産を守る重要な職業でありながら、公務員として安定した給与と待遇が魅力です。近年はその社会的な意義や、やりがいに注目が集まる一方で、具体的な給与水準や手当について知りたいという人も多いです。
そこで今回は、消防士の平均年収や初任給、民間職種との違い、資格による収入の変化について詳しく解説します。将来、消防士を目指している方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
消防士(消防官)の平均給与・年収は?

世の中には様々な種類の職業がある中で、今も昔も人気な職業、「公務員」。給与や身分が安定しているから、という理由で公務員を目指す人が多いですが、全職業と比較してどのくらい違うのでしょうか。
全職業の平均給与額は「民間給与の実態調査結果」(令和3年国税庁発表)によると、平均年収(正社員のみ)は約508万円でした。
ちなみに、「地方公務員給与実態調査」(令和4年総務省発表)の消防士の平均給与額は以下の通りです。
・平均給与月額合計(手当込み):約40万円
・平均ボーナス:約152万円
・平均年収:約632万円
冒頭の通り、勤務地域や勤続年数などにより変動の可能性はありますが、全職業の平均年収よりも消防士は124万円高いことがうかがえます。
消防士の初任給
消防士の初任給は、自治体の規模や採用区分によって差があります。たとえば東京都消防庁では、大卒程度のⅠ類試験で採用された場合、月給は約30万2,100円、高卒程度のⅢ類試験では約26万4,700円からスタートします。
これに通勤手当、住居手当、時間外手当、特殊勤務手当などが加算されるため、実際の手取り額や月収はさらに増加します。採用後は研修期間が設けられ、勤務評価や経験年数に応じて段階的に昇給していく点も特徴です。
消防士がもらえる諸手当
消防士の給与は、基本給だけでなく多くの手当が加算されることで、総収入が大きく変動します。これは、勤務の特殊性や危険性、生活支援の観点から設けられているもので、安定した生活を支える重要な要素です。主な手当には以下のようなものがあります。
地域手当
地域手当は、物価水準や生活コストに応じて支給され、東京都や大都市圏では支給額が高くなります。
住居手当
家賃を支払っている職員に対し、支給されます。訓練生の場合は、寮費がかからないケースもあります。
通勤手当
公共交通機関を利用する場合に、実費相当が支給されます。車通勤が認められている地域では、ガソリン代や距離に応じた手当が支給されることもあります。
扶養手当
配偶者や子どもなど扶養家族がいる場合に支給されます。配偶者、子どもの人数により扶養手当の金額は異なります。
時間外勤務手当(残業代)
災害対応や訓練、事務処理などにより勤務時間が延長した場合に支給されます。火災や救急の出動が多い部署では支給額が大きくなります。
特殊勤務手当
災害出動、救急対応、夜間勤務など、通常よりも危険や負担の大きい勤務に対して支給されます。現場ごとの条件や頻度に応じて支給額が異なります。
このように、消防士は単に公務員という安定性だけでなく、危険業務に従事する者としての補償が充実しているのが特徴です。
東京消防庁のような大都市圏では、これら手当の充実により年収が700万円を超えるケースもあり、勤続年数や階級が上がることでさらに高収入を目指せます。
試験の種類によって給与に差が出る場合がある
消防士として採用される際は、「どの試験に合格したか」によって、初任給や昇進スピード、将来のキャリアに差が出ることがあります。
主な試験区分には、「Ⅰ類(大卒程度)」「Ⅲ類(高卒程度)」「専門系(機械・電気など)」の3種類があり、それぞれで求められる能力や業務内容が異なります。
たとえば、東京消防庁では以下のような採用区分が設けられています。
東京消防庁の区分による収入の違い
| 試験区分 | 採用時の給与(月額) | 初年度推定年収(目安) |
| Ⅰ類(大卒程度) | 約30万2100円 | 約380万円〜 |
| Ⅲ類(高卒程度) | 約26万4700円 | 約310万円〜 |
| 専門系(機械・電気等) | 約30万6900円 | 約400万円〜 |
(参考:東京消防庁 採用情報-福利厚生)
Ⅰ類は主に大学卒業程度の学力を有する方が対象で、将来的には幹部職員としての登用が期待されます。その分、採用時の基本給もやや高く設定されています。Ⅲ類は高卒程度が対象で、若いうちから現場経験を積み重ねる実務型のルートです。
一方、専門系は設備管理や無線通信など、技術職に特化した人材を対象とし、特定の技能を活かした職務に就くことになります。このように、試験区分によってスタート時点の給与や今後のキャリアパスに違いが生じるため、自分が将来どのような働き方をしたいのかを見据えて受験区分を選ぶことが重要です。
階級が上がるにつれて給与も上がっていく
消防士は、明確な階級制度に基づいて給与が設定されており、勤続年数や実績、昇任試験の合格などに応じて、徐々に階級が上がっていきます。
階級は「消防士」からはじまり、経験を積みながら「消防副士長」「消防士長」と昇進し、やがて「消防司令補」「消防司令」、最終的には組織の指揮を執る「消防司令長」へとキャリアアップしていきます。初任時は「消防士」として現場での実務経験を積み、数年後に「消防副士長」や「消防士長」へと昇任するケースが一般的です。
階級が上がるにつれて役割や責任も増し、同時に基本給も高く設定されます。また、指導や管理を行う立場になることで役職手当や指揮手当などが加算され、月収・年収ともに大きく上がります。
たとえば、現場の最前線で活躍する階級から、部隊の管理を担当する階級へとキャリアアップすると、年収はおおよそ100万円以上増えることもあります。「消防司令」以上の管理職クラスになると、年収700万円〜800万円台に到達するケースもあります。
消防士の給与が他の職業と比べて高い理由
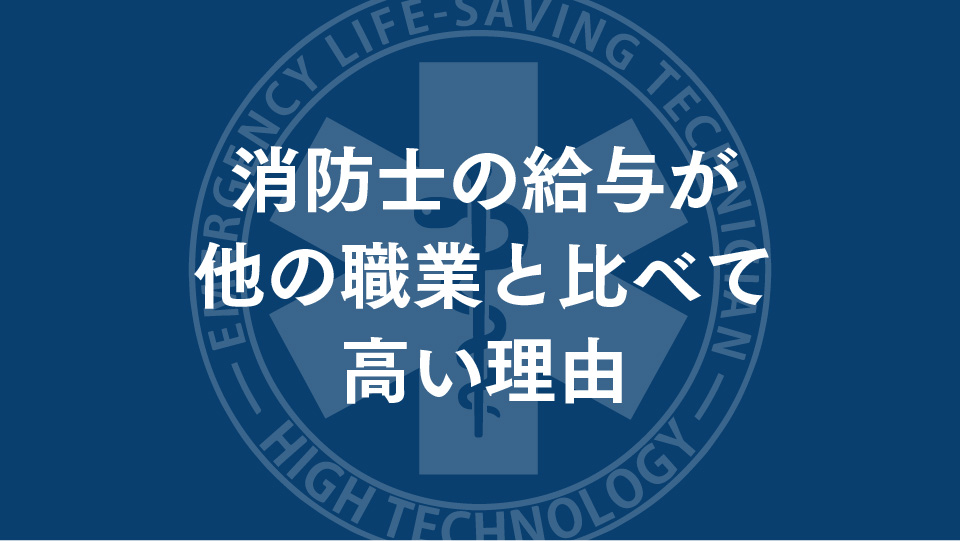
消防士は、ほかの職業と比べて給与が高いといわれています。ここでは、なぜ消防士の給与がほかよりも高いといわれているかについて解説します。
特殊勤務手当が設けられているから
消防士の業務には火災や災害現場への出動など、生命の危険が伴う場面が多くあります。こうした業務には特殊勤務手当が支給されるため、一般的な職種と比べて年収が高くなる傾向があります。
実際に、消火活動や救助活動の際には高温・有毒ガスなどの過酷な環境下での作業が伴い、命の危険もある仕事であるため、危険手当が支給されます。夜勤や24時間勤務といった勤務形態による負担も考慮されており、交代勤務手当や深夜勤務手当なども加算されます。手当は月々の給与に加算される形で支給され、年収全体を押し上げる大きな要因となっています。
公務員のため安定した待遇が受けられるから
消防士は地方公務員として採用されるため、給与や身分が安定しています。一般企業のように業績に左右されることがなく、景気に関わらず安定的にボーナスが支給されるほか、退職金も高水準である点が魅力です。
また、定期的な昇給や昇任制度が整っており、長期的に安定したキャリアを築けます。福利厚生も充実しており、健康保険や年金制度はもちろんのこと、住宅手当や扶養手当などが充実している自治体もあります。
有給休暇も確保されており、仕事と生活のバランスを保ちながら働くことができる点も、公務員ならではの強みです。
業務範囲を広げたい人は「救急救命士」の資格も取得しよう
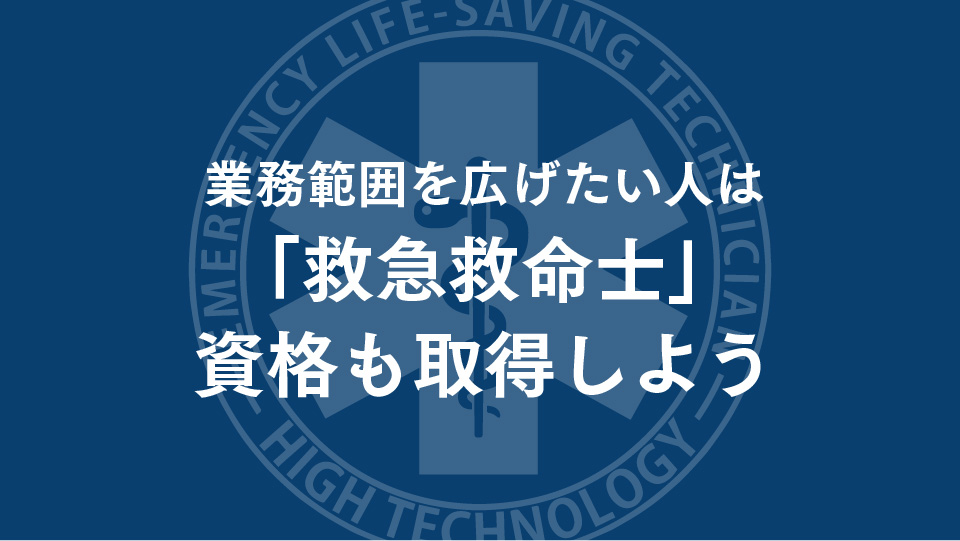
火災や交通事故、災害現場などに急行し、住民の安全を守る「消防士」。その中でも、より高度で専門的な応急処置を担う仕事が「救急救命士」です。また、救急救命士は「国家資格」でもあり、救急隊員の中でも特別な「救急救命処置」を行うことが可能です。
消防士と救急救命士の違いは?

一般の救急隊員も傷病者の救急処置を行うことができますが、救急救命士は救急隊員の中でもより高度で専門的な救命処置を行う「救急現場・人命救助のスペシャリスト」として、患者さんに最も早く接触して救助し、素早く病院へ搬送するお仕事です。
救急救命士は国家資格を持つ医療従事者として、一般の救急隊員にはできない点滴や薬剤投与、気管挿管などの特定行為を医師の指示のもとで実施できます。現場での判断力と高度な技術により、重篤な患者の容態を安定させ、医師による本格的な治療が受けられるまでの貴重な時間を確保します。消防署に所属する場合が多いものの、民間の救急搬送会社や病院でも活躍しており、24時間体制で市民の安全を守っています。
つまり、救急救命士は「病院まで命を繋ぎ、人生を繋ぐ」お仕事なのです。一刻一秒を争う緊迫した現場で、医学知識と冷静な判断力を駆使して、かけがえのない命を救う使命を担っています。
救急救命士になるには?

こんなに魅力的な救急救命士ですが、目指す方法は2通りあります。
1つ目は【消防署に就職し資格取得を目指す方法】です。
具体的には
消防署に就職し、5ヶ月間の消防学校初任教育を受ける
救急隊になるための資格を2ヶ月間、消防学校で教育を受け救急隊員へ
消防署で救急隊員として5年間もしくは2000時間以上の経験を積む
その後、消防署内で選抜試験を受け合格したら救急救命士養成所に入所
救急救命士養成所にて約6ヶ月間学習をして国家試験に合格する
5つのステージをクリアする必要があります。
この方法では救急救命士国家試験を受けるために何年もかかるケースも多く、その上での猛勉強のことを考えると大変険しい道であることは間違いありません…。
2つ目は【高校卒業後、養成学校に入学し資格取得を目指す方法】です。
具体的には以下の流れになります。
養成学校(専門学校もしくは大学)に通い
国家試験を受験し合格する
国家試験のため簡単な試験ではありませんが、この方法であれば卒業年次に国家試験を受験することができるので、1つ目の方法よりも、早く資格取得を目指すことが出来ます。
救急救命士 国家試験の合格率は?

救急救命士の国家試験は毎年1回実施され、全国から多くの受験者が挑戦する試験です。実技を想定した問題も出題されるため、合格には十分な準備が重要になります。
過去3年分の国家試験合格率は以下の通りです。
救急救命士の国家資格の合格確率
2023年:93.8%
2024年:94.2%
2025年:94.4%
まとめ
いかがでしたでしょうか?この記事を読んで、「救急救命士」について考える参考にしていただけたら幸いです。
第1回目の国家試験から30年以上にわたり受験生を支えてきた北海道ハイテクだから、あなたの目標が叶う!今後の更新もお楽しみに!
学科情報はこちら
消防士・救急救命士を目指すならハイテクへ!
各種手厚いサポートや機材・実習の様子を見学にいらしてください!
イベント申し込みは下記のバナーから!