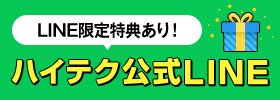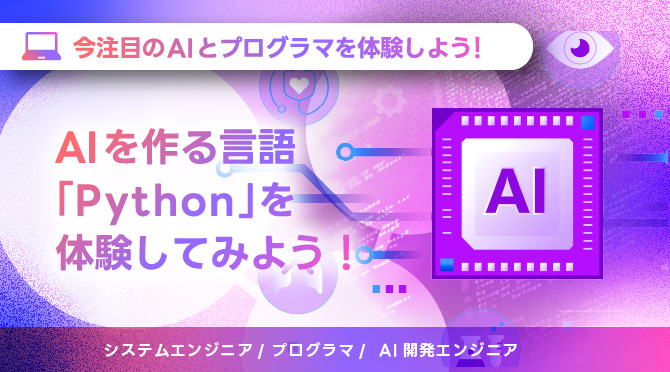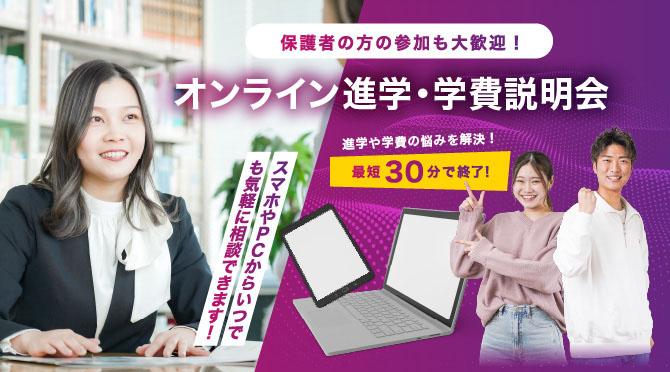AIエンジニアとは?仕事内容やなるために必要な知識を紹介!
「AIエンジニアという言葉は聞いたことがあるけれど、どのような仕事をしているのだろう?」そう思われる方もいるかもしれません。
スマートフォンや自動運転、ロボット掃除機など、私たちの身近な技術の裏側にあるのがAIです。そして、そのAIを作る仕事をするのが「AIエンジニア」という職業です。この記事では、AIエンジニアの仕事内容や必要なスキル、なるための道のりまでをわかりやすく解説します。
【目次】
AIエンジニアとは
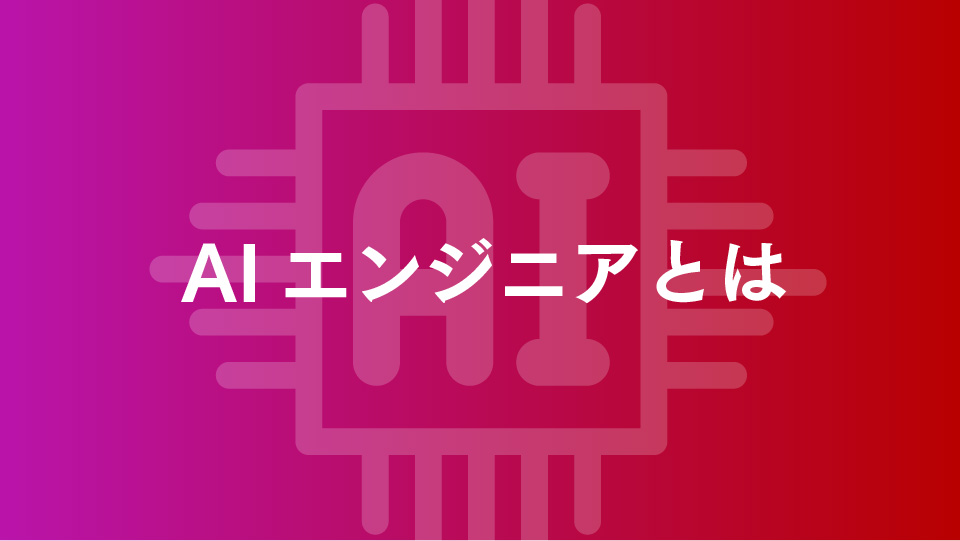
AIエンジニアとは、「人工知能(AI)」を開発・活用する専門家のことです。AIは私たちの生活にすでにたくさん使われています。たとえば、スマートスピーカーが話しかけたことに答えてくれたり、動画アプリが自分の好みに合った動画をおすすめしてくれたりするのもAIの力です。そして、これらを動かすためのプログラムを作るのが、AIエンジニアの仕事です。
AIエンジニアは、単にプログラムを書くだけでなく、AIが正しく判断できるようにどのような仕組みにするべきかを考えたり、大量のデータをもとに学習させたりと、さまざまな技術と知識を駆使してAIを育てていきます。最近では、工場の自動化や医療の診断支援、自動運転など、AIが活用される場面がどんどん広がっており、AIエンジニアの活躍の場も増え続けています。
ITエンジニアとの違い
「AIエンジニア」と「ITエンジニア」は、どちらも技術者という共通点がありますが、役割は少し異なります。
ITエンジニアは、システムやソフトウェア、ネットワークの設計・開発・運用など、コンピューター全般に関わる仕事をする人のことです。たとえば、企業の業務システムやスマホアプリを作ったり、ネットワークの安全を守ったりするのがITエンジニアです。また、ITエンジニアは基盤技術を扱うのに対し、AIエンジニアは最新技術を扱う、という違いがあります。
一方、AIエンジニアは、人工知能に特化した知識と技術を使ってAIを設計・開発します。とくに「機械学習」や「深層学習(ディープラーニング)」といった分野を活かし、人間のように判断したり予測したりするシステムを作ることが中心です。
つまり、ITエンジニアが便利なシステムを作る職業だとすれば、AIエンジニアは自分で考えて成長するシステムを作る職業で、AIの時代に求められる次世代型エンジニアともいえるでしょう。
北海道ハイテクノロジー専門学校では、無料でAI体験授業行っています。
AIエンジニアの仕事内容は?
AIエンジニアの仕事は、ただプログラムを作るだけではありません。AIが正しく学び、働けるようにするためには、さまざまなステップが必要です。ここでは、AIエンジニアが担当する主要な4つの業務をご紹介します。
情報収集・データ解析
AIを育てるためには、まず学習させる材料、つまり「データ」が必要です。AIエンジニアは、膨大なデータを集めて整理し、どのような特徴があるかを分析するところから始めます。
たとえば、画像認識AIを作る際には、さまざまな猫や犬の写真を大量に集め、「違い」を見つけられるようにします。また、チャットボットを開発する場合、「ユーザーがよく使う言葉」や「質問のパターン」をデータとして集め、分類・整理する必要があります。データの中に誤字やあいまいな表現がある場合も想定し、AIが正確に理解できるように前もって処理しておくこともAIエンジニアの仕事です。人と自然な会話ができるAIを作るには、こうした細かいデータの扱いがとても重要になります。
AIモデルの開発
データがそろったら、次はAIの「頭脳」となるモデルを作ります。これは、データからパターンを学習させることで、判断や予測ができるようになる仕組みのことです。AIモデルのなかの機械学習やディープラーニングといったさまざまな手法からどの手法を使うか、どのような条件で学習させるかによって、AIの精度や使いやすさが変わってきます。AIエンジニアは、理想的なパフォーマンスが出せるように、学習データや目的に応じて最適なモデルを設計・開発する役割を担います。
システム設計・実装
AIモデルが完成したら、実際に使えるようにするためにシステムに組み込む必要があります。たとえば、チャットボットにAIを搭載したり、スマホアプリに予測機能を追加したりといったことを行います。この段階では、AIをうまく動かすためのプログラミング技術や、使いやすいシステムを設計する力が求められます。ユーザーが自然に使えるように工夫することもAIエンジニアの重要な仕事のひとつです。
テストと分析
AIは学習するシステムですが、学んだことがすべて正しいとは限りません。だからこそ、開発後にはしっかりと「テスト」する必要があります。AIエンジニアはトラブルを防ぐために実際の動作を何度もテストし、間違いの原因を探して修正しAIの性能を高めていきます。
AIが間違った判断をしてしまうと、トラブルにつながることもあるため、テストと分析の工程はとても大切です。AIエンジニアは、性能を評価しながらよりよいAIに育てていく役割も担っています。
AIエンジニアが活躍する業界・分野
AIは今、さまざまな業界で活用されています。AIエンジニアは、業界ごとに異なる課題に対して、AIを活用して解決策を提供します。ここでは、AIエンジニアが活躍している代表的な業界と、具体的な事例をご紹介します。
自動車
自動運転技術の中心にあるのがAIです。AIエンジニアは、センサーで得られた情報から人や障害物を認識し、どう走るかを判断するアルゴリズムを開発しています。たとえば、カメラ映像を解析して信号や標識を認識する技術も、AIによって支えられています。さらにはAIによる自動化技術の進展は、車の製造工程全体を自動化する未来への可能性も秘めています。安全性と快適さを両立するクルマづくりには、AIエンジニアの力が不可欠です。
産業・製造業
工場の生産ラインでも、AIの導入が進んでいます。異常を自動で検知したり、品質をチェックしたりするAIシステムは、作業の効率化や不良品の削減に大きく貢献しています。また、製造業は少子高齢化の影響により、人手不足が深刻な問題です。そこでAIは限られた人員でも生産性を維持して高品質な製品を供給するために、人手に頼っている業務の一部を自動化して生産効率を向上させ品質管理を強化することに活用できます。AIエンジニアは、画像解析や予測分析の技術、さらには業務自動化の技術などを駆使して、スマートファクトリーの実現を支えています。
医療
保健医療分野では、AIの研究開発を主導する人材が不足しているといわれています。医療にAIを取り入れることで、病気の早期発見や診断支援、治療方法の提案などに活躍します。医療分野での臨床的知識を持つ医療AIエンジニアは、正確で信頼性の高い診断を可能にするAIを開発し、課題解決策を提案する人材として大切な業務を担います。
金融
近年、金融業界でもAIの導入が本格化しており、それに対応できる人材のニーズが高まっています。多くの企業では、現在働いている社員に向けてAIやデータ分析の基礎を学ぶ研修を導入したり、実務の中でどのようにAIを活用できるかを共に考える場を設けたりと、社内のスキル強化に取り組んでいます。
同時に、すぐに現場でAIを活かせる即戦力の人材を採用する動きも活発です。とくに、AIエンジニアといった専門職では、実務経験とスキルを兼ね備えた人材が強く求められています。
今後の金融業界では、AIの知識と金融の専門性を兼ね備えた人材がより一層重宝されていくでしょう。
小売り・EC
ネットショッピングサイトで「あなたへのおすすめ」が表示されるのは、AIがユーザーの行動を分析しているからです。また、在庫の最適化や価格の自動調整などもAIによって行われています。AIエンジニアは、購買データや行動ログを活用して、売上アップに直結するAIシステムを構築しています。
また、大手コンビニエンスストアでは新商品の企画立案プロセスにAIを導入することで、消費者の声を分析し、商品アイデアを出したり、企画書に記載する画像や文章を自動生成したりしています。これは、商品企画にかける時間を短縮し、開発スピードを向上させる効果が期待できます。
エンターテイメント・メディア
音楽や動画のおすすめ、ゲームのキャラクターの動き、さらにはCGの自動生成まで、エンタメの世界でもAIが活躍中です。AIエンジニアは、ユーザーの好みに合ったコンテンツを提案したり、よりリアルな表現を可能にしたりと、新しい体験をつくる役割を果たしています。エンターテインメント・メディア業界にAIが導入されることで、たとえばコンテンツ制作の自動化により業務効率化やコスト削減が狙えます。また、AIによるターゲティング分析でマーケティングも最適化できます。
環境・エネルギー
環境保全やエネルギー効率の向上にもAIが活用されています。たとえば、電力の需要予測や再生可能エネルギーの最適制御、環境モニタリングなどがその一例です。
AIは大量のデータを分析して、人間よりも正確にパターンや問題点を見つけるのが得意です。そのため、より正確な予測をしたり、仕事の効率を上げるアドバイスを出したりできます。
このような仕組みを考えて、AIをうまく動かせるように設計したり開発したりするのが、AIエンジニアの仕事です。エネルギー分野のようにAIの力が求められる現場が増えている今、AIエンジニアは社会のさまざまな場面で活躍できるでしょう。
農業
日本の農業は今、大きな転換期を迎えています。高齢化や後継者不足により、農業人口は年々減少しています。加えて、異常気象や自然災害の影響で作物の育ち方が不安定になり、農家の経営にも深刻な影響を与えています。さらに、安全性や品質、さらには生産の透明性といった、消費者のニーズも多様化しています。こうしたさまざまな課題を解決するために、今、農業の現場でもAIの導入が進んでいます。たとえば、ドローンと連携して作物の状態を分析したり、収穫時期を予測したりすることが可能です。AIエンジニアは、気候や土壌、作物のデータをうまく活用し、効率的で質の高い農業の実現に貢献しています。
AIエンジニアになるには?

AIエンジニアになるために、必須の国家資格などはありません。しかし、専門的な知識と技術が必要な職業のため、しっかりと学べる環境で基礎から身につけることがとても大切です。ここでは、AIエンジニアを目指すための学び方として、代表的な2つの進路をご紹介します。
【方法1】AIに特化した専門学校で学ぶ
AI分野に特化した専門学校では、現場で役立つスキルを実践形式で習得できます。特徴は、プログラミングやAIモデルの構築だけでなく、AIを使った課題解決やチームでの開発実習がある点です。大学に比べてより職業に直結した学びが多く、早く現場で活躍したい人に向いています。
また、業界と連携したカリキュラムやインターンシップを導入している学校も多く、就職に強いのも魅力です。AIエンジニアとしての基礎力を短期間で集中して身につけたい人にとって、有力な選択肢といえるでしょう。
【方法2】情報科学や工学部などの大学で学ぶ
大学の情報科学系や工学部では、AIに関連する理論を深く学びつつ、幅広い情報技術にも触れられます。また、数学や統計学、アルゴリズムといった基礎から研究レベルの知識まで段階的に身につけられるのが特徴です。
AIだけでなく、ネットワークやセキュリティ、ソフトウェア工学なども学ぶため、進路変更や応用範囲が広い点も大学進学のメリットです。一方で、実践的な開発経験や就職支援は学校によって差があるため、AIに特化したプロジェクトや研究室があるかどうか、進学先のカリキュラム内容をよく確認することが大切です。
AIエンジニアに求められる知識・スキル
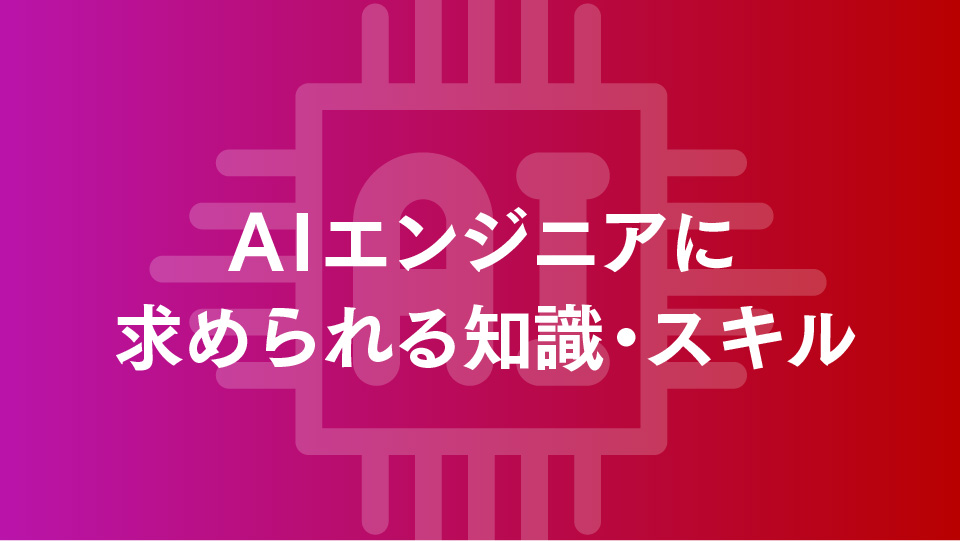
AIエンジニアとして活躍するためには、さまざまな技術と知識が必要です。ただし、はじめからすべてを完璧に理解している必要はありません。ここでは、AIエンジニアに求められる代表的なスキルを5つに分けてご紹介します。
プログラミングスキル
AIを動かすためには、プログラミングが必須です。Python(パイソン)はAI開発でよく使われる代表的な言語で、データ処理や機械学習との相性が抜群です。その他にも、JavaやC++、Rなどの言語も状況に応じて使われます。まずはPythonから始めるとよいでしょう。プログラミングスキルを学習する方法には、オンラインプラットフォームを活用したり、データ分析コンペティションに参加して実践的に経験を積んだりすることなどがあります。
機械学習の基礎アルゴリズム
AIの中核となるのが「機械学習(マシンラーニング)」です。これは、AIにたくさんのデータを学習させて、予測や判断ができるようにする仕組みのことです。決定木、SVM(サポートベクターマシン)、ニューラルネットワークなど、代表的なアルゴリズムの理解が求められます。
ソフトウェア開発
AIは単体で動くわけではなく、アプリやシステムに組み込まれて活用されます。そのため、AIを組み込んだソフトウェア開発の知識やスキルも重要です。とくに、チームでの開発や設計書の作成、バージョン管理ツール(Gitなど)の使い方を知っておくと現場で役立ちます。
統計学の基礎知識
AIは「データ」を使って判断するため、統計的な考え方も重要です。たとえば、平均や分散、相関関係など、基礎的な統計知識があると、データの意味を正しく読み取れるようになります。AIの精度を高めるうえでも、統計学は欠かせません。統計学と合わせて、微分積分や線形代数などの数学も一定レベルの知識があると役立つでしょう。
データに関するスキル
AI開発の前提となるのが「データ」です。データの収集方法、整形(クレンジング)、保存、管理など、データに関するスキルがなければ、AIもうまく機能しません。データベース(SQLなど)、テーブルの結合や集約への理解、クエリのパフォーマンス改善など、ビッグデータの扱い方も含めて、実務に直結するスキルです。
AIエンジニアの平均年収
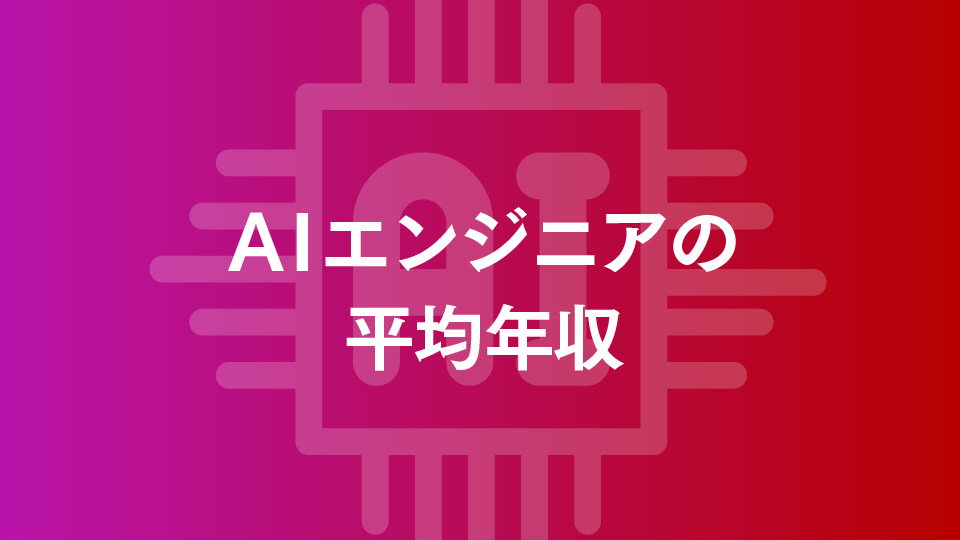
AIエンジニアの年収は、他のIT職種と比べても高い傾向にあります。日本国内の平均年収は約600万円とされており、経験やスキルによっては1,000万円を超えるケースもあります。とくに、ディープラーニングなど高度な技術に精通している人材や、プロジェクトマネジメントができる人材は企業から高く評価され、高収入を得ています。
また、AIエンジニアの需要が高まっている今、未経験からでも学習と経験を積めば、安定した収入を得られるチャンスが広がっています。将来性と収入の両方を重視する人にとって、魅力的な職業といえるでしょう。
AIエンジニアの将来性は?

AIエンジニアは、今後ますます活躍の場が広がると期待されている職業です。なぜ将来性があるのかを以下で、その具体的な理由を解説します。
幅広い産業で導入されているため需要が増加!
前述したようにAI技術は、製造業・医療・金融・小売・農業・エンタメなど、あらゆる業界で導入が進んでいます。それに伴い、「AIを活用できる人材=AIエンジニア」のニーズも増加しています。たとえば、病気の診断をサポートするAI、自動運転車を制御するAI、オンラインショップで顧客に最適な商品をおすすめするAIなど、現場での活用例は数え切れません。
生成AIの技術の進化に伴い、AIエンジニアの必要性の低下を懸念する声も聞かれます。しかし、生成AIの導入が進んでも、新しい知識やスキルを使ってシステムを設計・開発できる人材が今後も求められ続けるため、AIエンジニアは長期的に必要とされる職業といえるでしょう。
市場価値が高く年収も高い傾向にある
AIエンジニアは、高度な知識と技術を要する専門職であるため、市場価値も高い職種です。需要が高い一方で、十分なスキルを持つ人材がまだ少ないため、年収も高く設定される傾向にあります。
また、AI分野は急速に進化しているため、新しい技術を学び続けられる人にはキャリアアップのチャンスも豊富です。将来的には、プロジェクトマネージャーやリサーチャー、起業など多彩なキャリアパスが広がります。スキル次第で、国内外問わずグローバルに活躍する道も開かれるでしょう。
AIエンジニアになるために取得しておくとよい資格
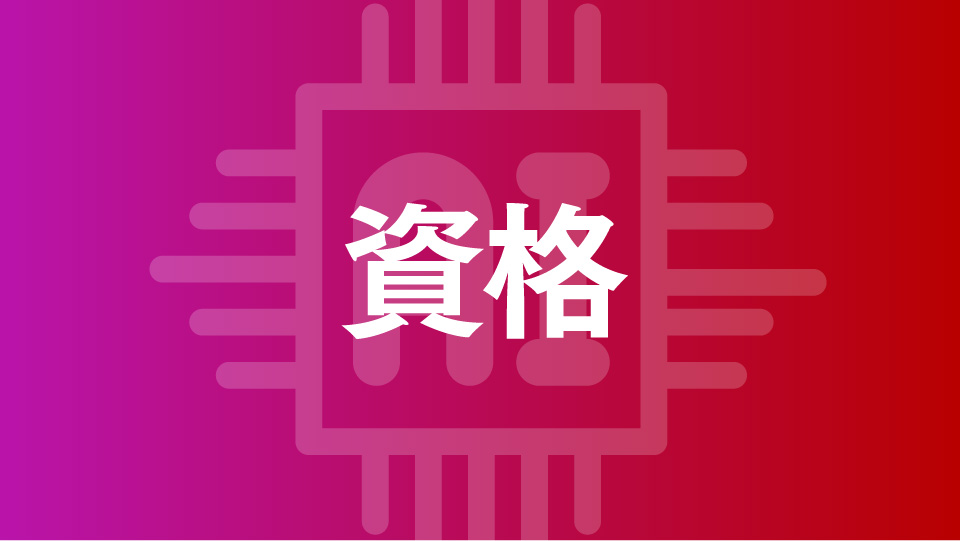
AIエンジニアになるために絶対に必要な資格はありませんが、知識の証明や就職活動でのアピールになるため、資格取得は大きな武器になります。また、資格取得の勉強を通して、体系的に知識を整理できるメリットもあります。ここでは、AIエンジニアを目指す人にとくにおすすめの3つの資格を紹介します。
G検定
G検定(ジェネラリスト検定)は、AIの基礎知識や活用方法を問う検定で、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催しています。AIに関する理論、活用事例、法律や倫理について幅広く学べる内容で、非技術職の人でも受験しやすいのが特徴です。AIを扱う上で必要な全体像を把握できるため、AI分野に興味がある高校生や初心者にとって第一歩としても有効な資格といえるでしょう。
E資格
E資格(エンジニア資格)もJDLAが主催しており、G検定よりも実践的・技術的な内容が問われる中級〜上級者向けの資格です。ニューラルネットワークやディープラーニングの実装スキルを身につけているかを証明できます。受験するためには、協会が認定する講座の受講が必要であり、一定のハードルはありますが、AIエンジニアとしての実力を客観的に示す強力な武器になります。企業からの評価も非常に高い資格です。
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験は、経済産業省が実施するIT全般に関する国家資格で、ITエンジニアの登竜門ともいわれています。AIをはじめ、ネットワーク、セキュリティ、プログラミングの基礎など、幅広いITスキルを習得できます。AIエンジニアになるための土台として、取得しておくと役立つ資格です。
とくに、高校生や専門学校生が初めて挑戦する資格としても人気があり、就職活動でも高く評価されます。インターネットや参考書を使って独学でも十分合格することが可能な試験のため、社会人の方でもスキマ時間を利用して資格取得のための学習ができるでしょう。
AIエンジニアに向いている人の特長
AIエンジニアは、専門的な知識や技術を活かしながら、日々進化する分野で活躍する職業です。ここでは、どのようなタイプの人がAIエンジニアに向いているのか、4つの特長に分けて解説します。
論理的思考力がある人
AIは「なぜこの結果になるのか」を理論的に説明できるシステムが求められます。そのため、物事を順序立てて考えられる「論理的思考力」はとても重要です。たとえば、バグやエラーの原因を冷静に分析し、最適な解決策を導ける人はAIエンジニアに向いています。論理的思考は、プログラミングのコードを書く際にも、効率的でよく整理されたコードを書く際に役立ちます。
ただし、論理的思考力といっても、難しく考える必要はありません。たとえば、数学の証明問題に順を追って取り組んだり、ゲームの攻略法を自分で見つけたりするような経験がある人は、自然と論理的思考を鍛えています。日常生活の中でも、「なぜこうなったのか」を考えるクセがある人は、AIの開発に向いているといえるでしょう。
探求心や好奇心が旺盛な人
AI分野は日々新しい技術や理論が生まれており、学び続ける姿勢が求められます。「なんでこうなるのだろう」「もっといい方法はないのか」などと探究することが好きな人は、AIエンジニアに向いているといえます。最新技術への探求心や好奇心が旺盛な人は、AIエンジニアとしての成長の原動力にもなるでしょう。
たとえば、新しいアプリやガジェットが出たときに「どうやって動いているのだろう?」と調べたくなるような人や、SNSで人気のAIツールを実際に使ってみたくなるような人は、すでに探求心のセンスがあります。AIの世界は1年で大きく技術が変わることもあるため、好奇心をもって学び続けられる人ほど変化に対応しやすく、成長スピードも速くなるでしょう。
問題解決能力が高い人
AI開発では、目の前の課題に対してどうアプローチするかが重要です。「このデータをどう使えばいいか」「このAIが失敗する原因はどこにあるか」など、常に課題に向き合い、具体的な解決方法を提案できる力が求められます。現状を見つめて改善し続けられる人は、AIエンジニアとして活躍できる素質があります。
ゲームをするのが好きな方なら、たとえば、ゲームの難関ステージで攻略方法を何パターンも試し、理科の実験で予想と違う結果が出たときに「なぜだろう?」と原因を考える経験は、まさに問題解決の練習になります。AI開発でも、完璧な正解が初めからあるわけではありません。小さなヒントを積み重ねて、最適な方法を見つけていく柔軟な考え方がとても役立ちます。
粘り強さがある人
AI開発は何日もかけて作ったプログラムがうまく動かないこともよくあり、試行錯誤の連続です。そのようなときに、一度の失敗で諦めるのではなく「もう一度試してみよう」と前向きに考えられる粘り強さが大きな武器になります。勉強や部活動でも、なかなか結果が出なくてもコツコツ取り組んできた経験がある人は、AIエンジニアに必要な素質を備えているといえるでしょう。諦めずにトライし続ける力が、未来のAIをつくる原動力になります。
AIエンジニアの学校の選び方
AIエンジニアを目指す上で、どの学校で学ぶかはとても重要なポイントです。実践的に学べるか、将来に役立つサポートがあるかなど、進学先によって学びの質は大きく変わります。ここでは、学校選びで注目したい4つのポイントをご紹介します。
カリキュラムの内容と質を確認する
まず大切なのは、「何を学べるか」です。AI分野に必要なプログラミング、機械学習、統計学などが体系的に学べるカリキュラムかをチェックしましょう。また、最新技術に対応しているか、実際に手を動かして学べる実習があるかも重要なポイントです。
もし未経験からAIエンジニアを目指す場合は、初心者向けのコースがあるかどうかもカリキュラムで確認しましょう。
就活サポートが手厚い学校を選ぶ
どれだけ知識を身につけても、それを活かせる就職先が見つからなければ学んだ内容を活かせません。だからこそ、就職サポート体制が整っている学校を選ぶことも大切です。企業説明会の実施や個別の面談、履歴書・面接対策など、手厚い支援がある学校を選ぶことで、自信を持って就職活動に臨めるでしょう。担任と就職担当、企業担当など、就活のステージに応じた担当がいる学校も安心材料のひとつです。
資格サポートに力を入れているかで選ぶ
資格は就職時の強いアピール材料になります。G検定や基本情報技術者など、AI・IT分野に役立つ資格の取得をサポートしてくれるかどうかは、学校選びの重要な基準です。たとえば、家庭で学習する代わりに放課後に対策講座や過去問題演習をしてくれるなど、学内で資格取得を後押しする体制が整った学校なら、資格を取ることで自信がつき、より高い目標にチャレンジする意欲も湧いてくるでしょう。
産学連携教育を取り入れている学校がおすすめ
実社会で役立つスキルを身につけたいなら、企業と連携して授業を行う「産学連携教育」に注目しましょう。産学連携教育とは、教育機関と企業が連携して行う教育プログラムのことで、実際の現場で使われている技術を学べたり、現役のプロから直接指導を受けられたりと、学校の中では得られない経験ができます。地元企業や先進企業と連携した実践教育を展開している学校なら、卒業後すぐに活躍できる力が身につきます。即戦力を目指したい人にとって、大きなアドバンテージになるでしょう。
まとめ | AIエンジニアを目指すなら北海道ハイテク
AIエンジニアは、今後の社会を支える非常に重要な存在です。この記事では、AIエンジニアの仕事内容や必要なスキル、将来性、なるための道のりなどを幅広くご紹介してきました。
「将来、何になればいいかわからない…」
そんな不安を抱えている人も、AIエンジニアという選択肢が新しい未来を開いてくれるかもしれません。情報分野に興味があるなら、将来の仕事につながる第一歩を踏み出してみませんか?
北海道ハイテクノロジー専門学校では、AI・IT・ビジネスの融合教育を通じて、時代に求められる人材を育成しています。就職サポートや資格支援も万全で、初心者でも安心して学び始められる環境が整っています。まずは、オープンキャンパスで学校の雰囲気や授業内容を体験してみてください。
IT、情報分野の専門学校なら北海道ハイテクノロジー専門学校へ。>>>